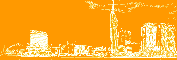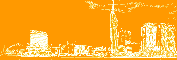|
本誌編集長の神崎公一郎が、さまざまな人をゲストに迎え、家族と暮らし、そして暮らしを支える住まいを中心テーマにリポートします。新シリーズ「福岡で暮らす」のトップコーナーとしてのスタートです。
第1回のゲストは、1998年から在福岡アメリカ領事館の主席領事を務めてこられたケビン・K・メアさん。この7月からは東京のアメリカ大使館公使に転任されましたが、福岡を離れるにあたり、福岡での生活を振り返って、子育てから住まいの在り方、さらには日米の文化の違いなど、幅広いテーマでお話を聞きました。
神崎 メア領事は外交官として東京、福岡での生活も長いわけですが、東京に比べた福岡の印象はいかがでしたか。
メア まず東京にあるものは、だいたい福岡にもありますね。しかも福岡はアクセスが良い。コンサートにしても、東京だとチケットも取りにくいけれど、福岡はそうでもない。私は東京に11年間住んでいましたが、人が多すぎてどこに行くにも時間の予測がつきにくい。その点、地理的に見て福岡はコンパクトな街ですね。都会の良さと共に地方の良さもあるし、伝統的な部分と現代的なところがあって面白い。文化も開放的。外食も便利ですね。
神崎 具体的にはどのようなことでしょうか。
メア レストランで言えば、天神で降りると、大名、親富孝通りなど店が集中していて見つけやすい。東京の場合は数が多すぎて、めざす店がどこにあるか分かりにくい。また、日常生活において東京より物価が安い。六本木のバーでビールの小瓶を注文すると、800円くらいですが福岡だと500円以下で済む。帰宅する際にも大きな違いがあります。東京はだいたい郊外に住んでいますから、終電の前に帰らなければならない。いっぽう福岡はタクシーを利用しても2、3000円で済むから深夜までお店が盛り上がっているわけです。
神崎 アメリカではホームパーティなどよくやられますか。
メア ハローウィンの時など、たまにはありますが、日本人が思っているほど多くはありません。確かに日本ではビジネスの接待など会食が多いわりに、夫婦や家族で外食というのは少ないかもしれません。
神崎 メア領事の奥様は日本の方ですが、アメリカと日本の家族で異なるのはどのようなことですか。
メア 私は典型的なアメリカの家庭人とは言えないかもしれないけれど、子どもの育て方には相異がありましたね。子どもたちがまだ小さい時に「厳しすぎる」と家内からよく言われたものです。日本は回りに迷惑をかけても「子どもだから仕方がない」という雰囲気で甘いでしょう。私は「子どものためになるから大人のように扱うべきだ」という姿勢でした。逆に子どもが大きくなると家内のほうが厳しくなった(笑)。
神崎 それはどうしてですか。
メア アメリカでは16才になればクルマの運転免許証を取れます。「人に迷惑をかけない。学校の成績を下げない」と、2つの条件で私は長男に許可しました。「もう16才なのだから自分で責任をとって判断すべきだ」と考えたのです。ところが家内は「16才はまだ子ども」という意識なのですね。私見ですが日本の多くの親たちは子どもに対して、くだらないことでうるさいと感じます。学校でも様々な規制があるでしょう。週末にスクーターに乗ったらダメ、化粧したらダメ、ピアスしたらダメとかね。それらは本来、学校の責任ではないのです。
神崎 子どもたちにしたら窮屈かもしれませんね。
メア 私は学校でホッケーなどの監督もしていたのですが、日本の監督を見ると、選手に対して「これはダメ、あれはダメ」と批判しているでしょう。時には「バカ野郎」と言って殴ったりもする。それは監督としては良くないと思いますよ。誰でも「ダメ」と言うのは簡単です。でも監督は何が正しいのかを選手に教えるべきです。子どもの育て方も同じで「子どもは小犬のように育てるべきだ」というのが私の持論です。
神崎 それはどのような意味なのでしょうか。
メア 小犬は自分の限界を知らないでしょう。そこで小犬が何か悪いことをしたら新聞紙で鼻をこするのです。犬にとって痛くはないけれど、鼻が敏感だからいやがります。毎回それを繰り返していると、小犬もだんだんと「やってはならないこと」を理解します。こうしたしつけを無視してしまったら良犬にはなりませんよね。しかも小さいうちに教えてやらないと、大きくなってから殴っても全く効かない。ですから子どもも小さい時にちゃんと時間を使って教えなければならないと思う。ダメで済ますのではなく、ちゃんと説明してあげるわけです。
神崎 さて住まいの件ですが、日本の住宅は子ども部屋が重視され、LDKという独特の形態が主流ですが、アメリカはどうですか。
メア 伝統的なアメリカの家にはリビング(応接室)とダイニング(客用)があって、台所は別れています。家の中で一番使われているのは台所とファミリールーム(日本のリビングルームに相当)ですね。リビングやダイニングはあるけれど、ほとんど使われていない。そこで最近のデザインはリビングを小さくして、台所がオープンな形でファミリールームとつながっているものがでてきました。お母さんは台所で仕事をしながら、ファミリールームで遊ぶ子どもやテレビを見たりできるようになっている。ダイニングは客人が来た時に使う部屋だから、田舎の家では台所にブレックファーストルームが隣接していました。今では昼食も夕食も、家族だけだったら、そこで食事するという流れです。
神崎 子ども部屋はどのような感じでしたか。
メア 私が子どもの頃は小さな家で、男3人の兄弟が同じベットルームでした。子どもの時は良いかもしれないけれど、ある程度成長したら別々な方が理想的でしょうね。
神崎 メア領事は公館にお住まいですが、日本の一般的な住宅で暮らした経験はありますか。
メア 日本に来て初めて住んだ住宅は2DKでした。当時は家内と2人で、まだ子どもはいなかったから特に不自由は感じませんでした。でも隣の家族は同じ間取りでも子どもが2人いらして、ご主人がかわいそうだと思いましたね。仕事から帰って来ても、幼い子ども達から逃げる場所がない(笑)。
神崎 家族の成長に合わせて住宅も変わっていくということですね。
メア そうですね。それと家族が一緒にいるのは、だいたい食事の時でしょう。あとはファミリールームで一緒にテレビを見たりする。でも時代の流れでライフスタイルも変化していくから、住宅のスタイルや価値観も進化していくでしょうね。
神崎 日本は土地も狭く住宅事情も良くないのですが、これはしかたありませんかね。
メア よくそう言われますが、工夫の余地があると感じます。不思議なことに、日本ではマンションの場合、間取りや広さがどの建設会社でもあらかじめ決まっているみたいですね。私は専門家ではないが、土地の大きさが決まっていても、高層マンションにすれば一部屋当たりの広さも大きくできるし、レイアウトだってもっと多様性があって良いはずです。ニューヨークだって土地が狭くて価格も高いけれど、コンドミニアムのような広い家もありますからね。日本のユーザーや建設業者が「しかたがない」と思っているうちは変わらないかも知れません。
神崎 それから日本では出生率が下がっていますが、将来は家族の在り方も変わっていくのでしょうか。
メア アメリカも日本ほどではないでしょうが、同様な傾向にあります。確かに出生率があまりにも低くなると社会的に問題はでてきますね。労働力の不足、特に老人が増えるわけだから介護の問題は深刻になるでしょう。アメリカは出生率が下がっていても人口は増えている。それは伝統的に移民が多いからです。日本でもこれから移民が増えるかどうか注目したいですね。過去において日本には鎖国時代もあったし、移民の伝統がない。これから日本の社会、文化が直面しなければならない問題の一つです。
アメリカでは外国の人でも永住権を取得してから5年間住んだらアメリカ人になれますが、日本で外国人が国籍を取得するのは非常に困難です。ただバブル期は出稼ぎ目的の流入が多かったけれど、今は永住のため日本にやって来ています。これは新しい現象ですね。
神崎 文化の国際化は時間がかかる話ですね。メア領事のオフィスにもこうしてご家族の写真が飾られていますが、日本ではなかなか見受けられませんからね。
メア 日本の方も別に家族を無視しているわけではないと思いますよ。でも職場で写真を置いたら同僚にいじめられるかもしれないのかな(笑)。
|